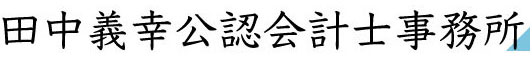コラム
川は流れる
2025年8月20日
病気で枯れた葉のことを、病葉と書いて、「わくらば」と読む。多くの人がこの言葉になじんだのは、仲宗根美樹の『川は流れる』を聞いてからではないか。沖縄にいた両親が戦火を避け東京に疎開して生まれた仲宗根美樹、本名国場勝子は、「病葉をきょうも浮かべて、街の谷、川は流れる」と歌った。60年安保の翌年である。大阪生まれで浪花けい子から芸名を変えた西田佐知子が同じ年に歌ったのは、『アカシアの雨がやむとき』だった。「アカシアの雨に打たれて、このまま死んでしまいたい」と。なぜ、こんなに暗い歌が流行っていたのか。当時の人々のもの悲しさを求める心情にぴったり合っていたからに違いない。
横堀川、紀ノ川、四万十川と、たて続けに川の名を題名にしている映画を見た。横堀川が大阪の船場をイメージさせるためだけの命名なのに対して、紀ノ川や四万十川は川自体が映画の主役ともいうべき大事な舞台装置になっている。
それで、故郷の甲突川(こうつきがわ)のことが思い出された。甲突川は、子どものころ祖父と遊んだ記憶を今もとどめている懐かしい川なのだが、案内を見ると、「鹿児島市の市街地を南北に分けながら錦江湾にそそぐ二級河川」とそっけない。甲突川は、民謡の鹿児島おはら節にも歌われている。「雨も降らないのに甲突川の水が色づいている、上流の方の伊敷あたりの女性のお化粧がとれて流れてきているのではないか」と。
その伊敷に祖父の家があり、甲突川からは歩いて五分とかからなかった。祖父は、むかしは商売をしていたらしいが、お盆には親戚一堂が集って一晩か二晩は泊まっていたので、家はそれなりに大きい造りだったのだろう。憶えているのは、広い土間の真ん中に井戸があってその水をポンプで汲みだして、風呂の水にしたり、たらいにためてスイカを冷やしたりしていたことだ。祖父に連れられて甲突川でひとしきり遊んで帰ると、その冷たい水が待っていて頭から浴びせられた。
祖父の家にはお婆さんもいたが、祖母ではなく、〇〇さんと名前で呼ばれていた。子ども心に後妻だということは肯けたが、その前はずっと祖父のお妾をしていたらしいことをだいぶ後になって知った。
二十世紀の終わりに洪水があって、甲突川にかかっていた石橋もいくつか消えた。甲突川にまつわる様々な記憶も、恩讐のかなたに押し流されつつある。