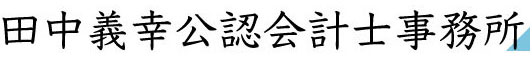コラム
神様は文学をする
2025年7月18日
この世に神様が〜本当にいるなら〜♪と歌う島倉千代子の『愛のさざなみ』が、巷に流れていたのは今から十五年前の二〇〇九年ごろのことだった。その頃、ふと思ったのは、この世に神様がいて、市井の人になりすましてどこかにひっそりと暮らしているとしたら、その人は生業としていったい何をしているだろうということだった。
それで、神様はまさか政治家や実業家にはなってはいないだろうとまず思った。政治の権力をめぐる争いや、市場での富をめぐる競争に、絶対勝者であるはずの全知全能の神様が身を置くはずがない。神様は、上昇志向の強い人間たちのいじましい営みをひたすら静観することに努めるだろう。
それでは、医師や裁判官などはどうだろうか。それはやはり神様が干渉してはいけない領域だと考えるのではないか。人間には様々な限界や過ちが多くあったとしても、神の手を下してはいけない、人間に任せるべきなのだと。
数学者や物理学者、天文学者などはどうだろうか。全知全能の神様なら、正しい答えを導くのはたやすいが、そもそも答えのある領域には近づかないだろう。正しい答えを求めて苦闘する人間がいることが、人間社会の一つの意義なのだと思うだろうから。
作家や画家はどうだろうか。神様の全知全能をもってしても、人間の作品にはかなわないと思うのではないか。なぜなら、文学作品や芸術作品は、人間の美徳だけでなく、人間の悪徳、堕落、頽廃、愚かさ、弱さなど、神様には及ばないところがないまぜになって、はじめて出来上がっているものだからである。そういうものに神様が手を出すはずがない。
それじゃ、いったい神様は何を生業にしている。僕は、神様は、市井に潜んで地味な文学の研究者をしているのではないかと考えた。様々な人間の営みの中で内外の古典や少し前の時代の文学作品に込められたものを研究する。それも自分が全知全能であることはわかっているのだから、小林秀雄のように自己を吐露したり、主張したりする必要はない。人間のいじましく、いじらしい営みをじっと観察するだけである。それには、ロシア文学なども悪くはないが、昭和の日本文学などはうってつけではないかと思った。