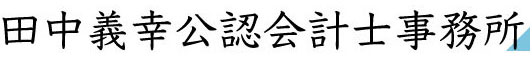コラム
めだかのがっこう
2025年11月20日
イヴァン・イリイッチの『脱学校の社会』は、本棚に同じものが三冊あるのに気が付いて、しょうがないなと思っていたら、蔵書を全部処分したときに奥からもう一冊同じものが出てきてあきれたことがあった。余程『脱学校-』という標題をみると買わずにいられなくなるような衝動が心の奥に潜んでいたのだろう。
前にアフガニスタンで若い女性がインタビューに答えて、「女性の大学教育が停止されているので学べない」といっているのを聞いて馬鹿々々しいと思った。それから、アマゾンの奥地で暮らす原住民のドキュメンタリーを見ていたら、若者がアマゾンでの生活から様々なことを学べることを例えて「アマゾンは僕の大学です」などと言うのを聞いて、「アマゾンが泣くぜ」と言いたかった。なぜそんなに学校幻想にとらわれるのか。ちなみに、僕は学校で教えたことはあっても、学校で教わったことはない。
学校は、戦前から戦後のある時期までは確実に少年や少女たちの救いの場になっていたと思う。映画『二十四の瞳』は作りものだが、学校がかつて少年や少女たちにとってどういう存在であったかを教えてくれる。それがある時期から、そうではない場所に変わり、今では全く救いの場ではなくなった。
ところで、あるとき大富豪のFさんから「田中さんはお金があったら何をやりたい?」と聞かれて、とっさに「小学校をやりたい」という答えが自分の口から出てきて、自分でも驚いたことがあった。そのときの僕には、今の小学校は知るべきことをなぞっているだけで、知るべきことをちゃんと教えていないという確信があった。
人には、先天的に記憶と思考、それから勘が働くという機能は備わっているが、理解という機能は必ずしも備わっていないように感じる。その理解という機能を開発して備えさせるようにするのが学校の役割だと思うが、学校がその役割を果たしていないというのが僕の感じていることである。
ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』を初めて読んだ。父親の書庫と図書館に入り浸って、ほとんど学校へ行かなかった彼女の才能の在りように驚く。「幸せだった」という遺書を残して、五十九歳で自死している。どこかで自己懲罰の意識が生じてそれが終生消えなかったのではないかと、我が身に引き直して想像するほかはない。